目次
『罹災証明書』(りさいしょうめいしょ)とは、災害の被害に遭った時に家屋の被害状況などを、各市町村(自治体)が調査をして、被害状況に応じて認定を行い、証明するものですが
普段、あまり耳にする事の無い
『罹災証明書』とは?
発行はどこでされるのか?
基準や期間など、システムや手順についても調べてみたいと思います。
罹災証明書とは?どこで発行されるのか?
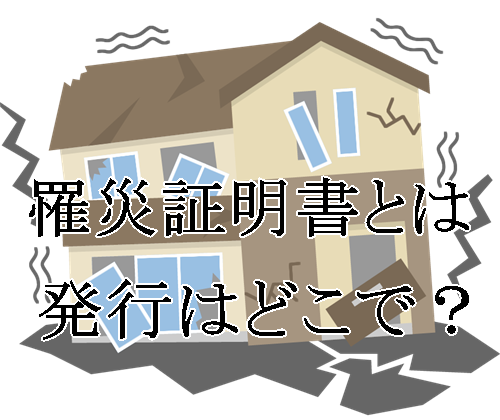
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは?
あまり聞くことが無い言葉なのも当然の事ですが、災害に遭ってしまった時に、とても重要な証明書になります。
今回は、罹災証明書について
学んでみたいと思います。
災害に遭った人の事を『罹災者』と言い、住んでいる家屋の被害状況の調査を各市町村が行い、それを証明するものを『罹災証明書』と言います。
簡単に言うと
『全壊』『大規模半壊』『半壊』『一部損壊』のどれなのか?
これらの認定により、特に『大規模半壊』なのか『半壊』なのかにより、大きく支援の内容も異なって来ます。
では、罹災証明書はどこで発行されるのかと言うと
罹災証明書は、市町村で交付されます。
しかし、この罹災証明の発行を行うのは
地震の場合→税務所家屋係
火災の場合→消防所
となります。
なので、罹災証明の調査などが
どこまで進行しているのか?
などを聞きたい場合は、発行を行う各税務所や消防所になります。
罹災証明書の注意点は・・・
各市町村により発行体制が異なるため確認が必要です!
罹災証明書を受けるにあたり気を付ける事は?
建物の損壊・損傷については、状況写真が必要になります。携帯電話・スマートフォンで撮影したもので良いので窓口に持参しましょう。
この時、可能な限り内部・外部・敷地・地盤など建物の損害を写真に多く残しておく事をおすすめします!
罹災証明書の手続きの手順は?

では、罹災証明書発行までの手順と流れはどうなっているのか?
罹災証明書発行までの手順と流れ
1,罹災証明書の発行を自治体に申請
↓
2,自治体の審査員が現場の被害状況を調査
↓
3,自治体が被害の程度を認定し、罹災証明書を発行する
この手順にあります、自治体の審査員が被害状況を調査とありますが
その基準はどうなっているのか?
住宅被害認定調査の基準について調べてみたいと思います。
罹災証明書の被害認定調査の基準は?
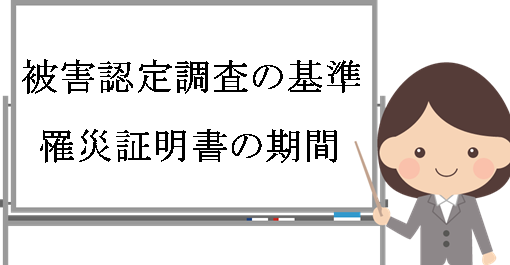
住家の被害の程度について、国で被害認定基準が定められています。
住家の屋根・壁等の被害の全体に占める割合に基づき、被害の程度を認定されます。
全壊→50%以上
大規模半壊→40%以上50%未満
半壊→20%以上40%未満
調査の方法は
被害認定調査について、国で標準的な調査方法を定めています。
具体的には、研修を受けた調査員(市町村の職員等)が、原則として2人以上のグループで被災した住家を傾斜・屋根・壁の損傷状況を調査します。
調査の流れは
第1次調査
外観目視調査
・一見して全壊か否かを判定
第1次判定の調査結果に
意義があれば
↓
第2次調査
外観目視調査及び内部立入調査
となります。
※第1次審査は、目視とある様に簡単な外観だけの調査です。2次審査を依頼することをおすすめします。
では、罹災証明書を発行してもらう事でどんな支援があるのか?
【公的支援】
・被害のあった家屋や土地の固定資産税・国民保険料が、一時的に減免される可能性がある。
・被災者生活再建支援金・義援金を受けられる。
・公的書類の手数料が無料になる。
・仮設住宅・公営住宅への入居が優先的に認められる。
・災害復興住宅融資が受けられる。
【民間支援】
・金融機関が、有利な条件で融資を行なってくれる場合がある。
・私立学校など授業料免除の可能性がある。
・災害保険の保険料を受給する事が出来る。
※自治体によって色々な支援制度があるので、ホームページで確認すると良いと思います。
ここでの注意点は・・・
一部の修理により居住が可能となる場合には、災害救助法に基づき『応急修理』を受けられる場合があります。
業者への委託は被災者からでは無く、各市町村から行う必要がある為、自ら業者に委託する前に、各市町村の窓口で相談しましょう!
罹災証明書の申請の期間について
申請期間は
1,基礎支援金は
災害発生日から13月以内
2,加算支援金
災害発生から37月以内
申請に必要な書面は
・支援金支給申請書
・住民票等
・罹災証明書
・預金通帳の写し
・その他関係書類
契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借等)
となります。
支援金支給までの手続きのシステムは?
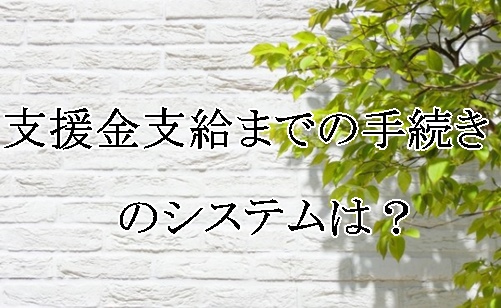
支援金が支給されるまでの流れ、システムはどうなっているのかを簡単にまとめました。
支援金支給までの流れは
1,支援法適用(都道府県)
↓
2,都道府県から、国・支援法人・市町村に適用報告・公示(都道府県)
↓
3,罹災証明書の交付(市区町村)
↓
4,支援金支給申請(被災世帯)
↓
5,市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付
↓
6,被災世帯に支援金の支給(支援法人)
↓
7,支援法人から国に補助金申請
↓
8,国から支援法人に補助金交付
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて
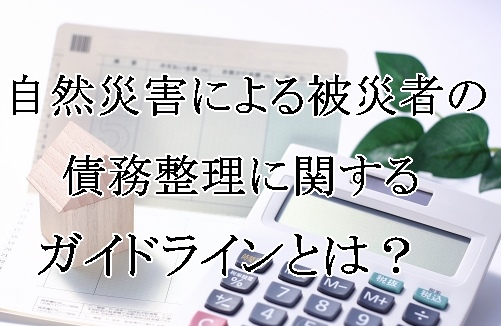
災害に遭って家が
住宅ローンを支払う余裕がない…
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにより、住宅ローン等の免除・減額を受けられることがあります。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
1,弁護士(登録支援専門家)による手続き支援を無料で受けられる。
2,財産の一部を手元に残してローンの支払い免除・減額等を受けられる。
3,破産等の手続きと異なり、債務整理をした事は個人情報として登録されない為、新たにローンを組む時に不利益なし
4,原則、連帯保証人も支払いをしなくて良くなる
などのメリットがあります。
義援金等を手元に残して、ローンの減額・免除を受けられる場合があるので、まずは弁護士に相談する事をおすすめします!
⇒食べるマスクがインフルエンザやアレルギーに?口コミやカロリーも!
⇒ラストレターの撮影&ロケ地は?キャストと内容は?エキストラ募集も
⇒333入浴法のやり方!カロリー消費で簡単に痩せたい!冷え性にも?
罹災証明書の発行はどこで?基準や期間は?の最後に
罹災証明書について調べさせて頂きました。
災害に遭ってしまった時に、必要となる罹災証明書なのですが
いざと言う時に、良く分からないと言うのが現実です。
インターネットで調べたくても、市のホームページが分かりにくかったり
年配の方などは、ガラケーで見られない・パソコンの使い方すら分からない
更に、被災者は家に住む事が出来ない状態になると、地域を離れる場合もあるので
全く孤立してしまう場合もあるのです。
自身の住む町が、地震などの災害にあった時のガイドラインの確認は大切だと、災害に遭って初めて感じた次第です。
何かのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。


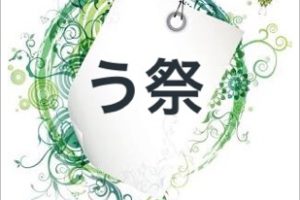

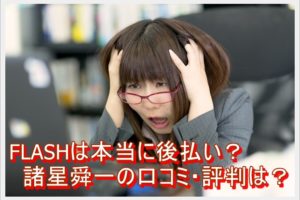












コメントを残す